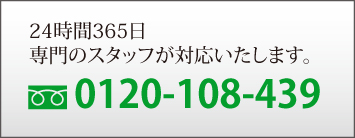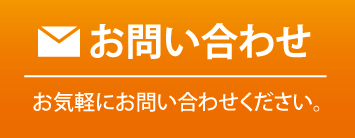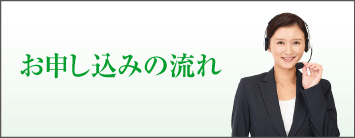お焼香(おしょうこう)とは

お焼香とは、仏式(僧侶にお経を読んでもらうスタイル)の葬儀や法事で、仏や死者に向けて香を焚いて拝むことを言います。
お葬式や法要などで、細かくした香を香炉に落として焚きます。心と身体の穢れ(けがれ)を取り除いて清浄な心でお参りするための作法で、一般的に左手に数珠を掛けて右手でお焼香を行います。
お焼香の種類
一般的なお葬式の焼香のやり方です。りつれい・りゅうれいと読みます。
椅子の会場ではなく畳です。やり方は立礼焼香と基本的に同じです。
自宅でのお葬式や狭い会場、法事などでのやり方です。お盆に乗った香と香炉が回ってきます。
抹香ではなく線香を使ったやり方です。法事で多いやり方ですが、お通夜で用いられることもあります。
お焼香の順番
焼香の順番は故人との関係が深い順です。
喪主→遺族→親族→参列者という順番が一般的で、関西地方などでは一番最後に止め焼香(留め焼香)があります。
葬儀会場では焼香の順番についてアナウンスされることも多いです。そして参列者の中では順番は特にないので自分がいつ焼香をするかはあまり不安にならなくても大丈夫です。
基本的なお焼香の方法
基本的なご焼香の方法は、まず、右手の親指・人差し指・中指の三本で抹香(香木を砕いた細かい木片)を少量つまみ、手を返して額の高さまでかかげます。(これを「押しいただく」といいます)
次に、左の香炉(炭の方)の少し上に移動させ、指をこすりながらパラパラと落とします。
このとき、数珠は左手にかけておきます。
宗派によって違いがありますが、あくまで故人のご冥福を心を込めて祈る気持ちが大切です。
立礼焼香のやり方
1.僧侶(いれば)に一礼、遺族に一礼
2.焼香台の1〜2歩手前で遺影に合掌して一礼
3.焼香台の手前に進み、左手にお数珠をかけ胸の高さに
4.左手はそのままで右手の3本指で抹香をつまむ
5.軽く頭を下げ、おしいただき(抹香を額の高さにささげる)香炉へ静かに落とす
6.宗派によっては3と4を繰り返す(1〜3回)
7.遺影に合掌し冥福を祈る
8.遺影に一礼
9.再び僧侶・ご遺族に一礼
大きな会場では2、3人同時にお焼香することもあります。その場合は一緒にお焼香をした人たちと同じタイミングで霊前から去りましょう。
座礼焼香のやり方
1.腰を屈めて焼香台へ向かい、ご遺族に一礼、遺影(ご本尊)に一礼。
2.座布団の前で両手を使って膝立ちし、にじり寄って正座したら、ご焼香は立礼と同じ方法で行います。
3.ご焼香が済んだら、遺影(ご本尊)に向かって合掌します。
4.両手を使って膝立ちし、そのままの姿勢で後退し、中腰になったら僧侶・ご遺族に一礼して、中腰のまま席に戻ります。
畳の部屋で座布団に座るので焼香台もその高さに合わせてあります。
座礼焼香のやり方は立礼焼香とほとんど同じです。
違うのは移動の仕方です。焼香台に近い場所に座っていた時は移動する場合に立ち上がらないようにします。膝を交互に動かしましょう。
または両手のこぶしを畳について前に体を進ませます。
回し焼香のやり方
1.香の乗ったお盆が回ってきたら、回してくれた人に会釈をする
2.自分の膝の前に置く
3.祭壇の遺影に向かって一礼をする
4.数珠を左手にかけ胸の高さに
5.左手はそのままで右手の3本指で抹香をつまむ
6.軽く頭を下げ、おしいただき(抹香を自分の目の高さにささげる)香炉へ静かに落とす
7.宗派によっては4と5を繰り返す(1〜3回)
8.数珠を両手にかけ合掌
9.お盆を両手で持ち次の人へ回す
膝の前にお盆を置けない場合は、自分の膝の上に置き左手でお盆を支えながら焼香します。右手だけですることになりますが問題ありません。
線香焼香のやり方
抹香ではなく線香を使います。1本か3本です。
臨済宗…一本立てます
真言宗…離して3本立てます
浄土真宗…折って横に寝かせます
日蓮宗…一本立てます
やり方は座礼焼香と同じやり方ですが、4〜5を以下のようにします。
・手で線香を持ちろうそくに火をつけ、線香を振るか、手であおいで火を消す
・線香が立ててあるときはくっつかないように立て、寝かせてあるときは同じように寝かせる
火を消すときに吹き消さないように注意しましょう。